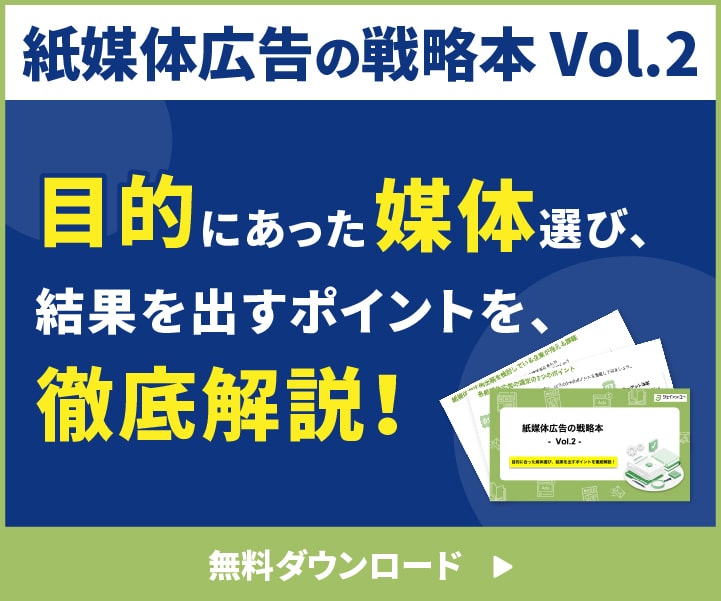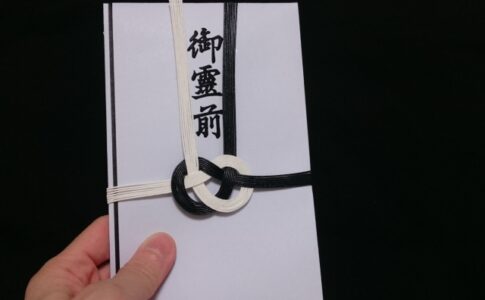病院が出す広告には、医療広告ガイドラインという厳格なルールがあります。患者さんに的確な情報を届けるのはもちろん、ルールを守ることが重要です。
この記事では、病院広告の基本的な知識から、必ず押さえておくべき医療広告ガイドラインの詳細、ついやってしまいがちなNG表現を紹介します。
さらに、患者さんの心に響く広告デザインの秘訣、費用対効果のある媒体選び、違反リスクを防ぐ具体的な対策まで、網羅的に解説していきます。
この記事を読めば、病院広告に関する疑問や不安が解消され、自信を持って広告戦略を立てられるでしょう。
また弊社では、紙媒体の広告の出稿をご検討の方に「紙媒体広告の戦略本Vol.2」を紹介しています。
詳しく知りたい方はぜひバナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。
目次
病院広告の基礎知識

病院広告は、病院やクリニックの存在や診療科目を地域の方々や患者さんに知ってもらう活動です。
ここでは、なぜ病院広告が大事なのか、どういった種類の広告があるのかを解説します。
病院広告が必要な理由
病院広告は、患者を確実に集めるには欠かせない要素です。実際、多くの患者は不調を感じるとスマホで病院を検索します。Web広告やサイトがなければ存在すら知られません。
広告で診療科目や病院の理念を伝えることで、競合との差別化や患者とのミスマッチ防止にも役立ちます。病院広告は患者とのコミュニケーションを支えるものであり、病院経営にも欠かせないといえるでしょう。
病院広告の種類と特徴
病院広告には「オンライン広告」と「オフライン広告」の2種類があります。オンライン広告ではWebサイトやSEO、MEO、SNSなどを活用し、低コストで特定のターゲットに効果的にアプローチできます。
一方、オフライン広告は看板や交通広告、チラシ、フリーペーパーなどであり、地域全体に広く認知させることが得意ですが、費用が高く対象を絞りにくい面があります。目的や予算に応じて、これらを組み合わせるのが効果的です。
なお、薬局広告について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインについて
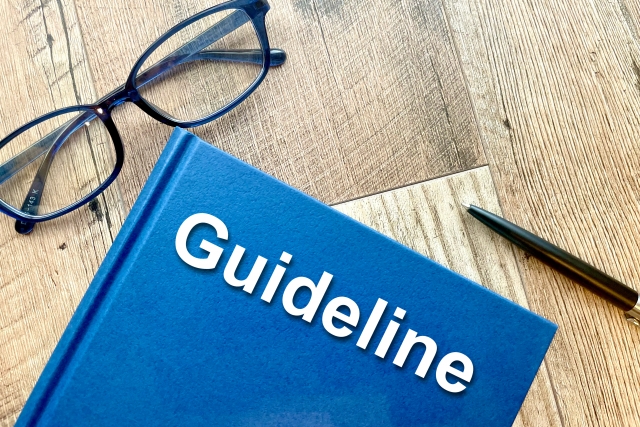
医療広告ガイドラインとは厚生労働省が定めた病院広告のルールブックです。
ここでは、ガイドラインの基本から注意点まで詳しく見ていきます。
医療広告ガイドラインとは?
医療広告ガイドラインとは、病院や歯科医院などが守るべき広告ルールです。正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。
医療広告ガイドラインは、患者保護と正確な情報提供を目的としています。「誘引性(患者を呼び込む意図)」と「特定性(広告主が特定可能)」を持つものは広告とみなされます。看板やホームページ、SNSなども対象です。
違反すれば罰則があるため、十分な理解が必要です。
医療広告ガイドラインの違反事例
ここでは、よくある医療広告ガイドラインの違反事例を表にまとめました。掲示している病院広告が規約に抵触していないか確認してみましょう。
| 違反内容 | 詳細 | 具体例 |
| 虚偽広告 | 全く事実と異なる経歴や、根拠が薄い情報を掲載した広告 | 「副作用は一切ありません」 「〇〇治療の成功率100%」 |
| 比較優良広告 | 他の病院と比較して、優れている点をアピールする広告 *客観的な事実に基づかない比較は認められません | 「〇〇地域でNo.1の実績」 「△△クリニックより優れた治療法を提供」 |
| 誇大広告 | 事実を過剰に強調、または実際よりも著しく優秀に見せかける広告 | 「どんな難病も治します」 「医師全員が〇〇学会の権威」 |
| 患者さんの体験談 | 治療の内容・効果に関する、主観的な体験談や感想を掲載すること *個人の感想は正当な評価とは言えないため、原則として禁止 | 「〇〇クリニックの治療は他とは違うアプローチがあります(30代女性)」 |
| Before/After写真 | 術前術後の写真やイラストを過度に盛る行為 | 加工・修正を加えた画像の添付 |
医療広告ガイドラインの改正ポイント
医療広告ガイドラインの改正で重要なのは、Webサイトが新たに広告規制の対象となった点です。
「誘引性」と「特定性」を満たすサイトは規制対象です。ただし、「限定解除要件」を満たすと一部の禁止事項も掲載できます。問い合わせ先や自由診療の費用、リスクの明示などが含まれます。
SNS活用やインフルエンサー依頼も広告に該当するため、適切な運用と最新情報の把握が必要です。
医療広告ガイドラインQ&A
医療広告ガイドラインのQ&Aをわかりやすく表にまとめました。気になる疑問点についてチェックしてみてください。
| 質問 | 回答 |
| 病院のWebサイトも対象になる? | 原則、患者を集める意図があり病院名が特定できるものは対象。ただし、情報提供目的なら対象外の場合もあり。 |
| 自由診療の広告は厳しい? | 厳しい。治療法、費用、副作用などの明記が義務付けられている。 |
| 広告内容が不安な時の相談先は? | 管轄の保健所、医療広告に詳しい弁護士や広告代理店、コンサル会社などに相談するのがよい。 |
| 違反するとどうなる? | 行政指導が入り、悪質な場合は広告の中止命令、罰金(最大30万円)、懲役刑などがある。病院の信用低下にもつながる。 |
医師に向けた広告について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
病院広告でできないこと4選

ここでは、病院広告でできないこと、広告に関する制限の内容を4つに絞って解説します。
誇大広告
誇大広告とは、提供する医療サービスの概要や効能について、事実を不当に誇張したり、過剰に見せたりする表現です。誇大広告には患者さんに過度な期待を抱かせ、冷静な判断を妨げる恐れがあります。
病院なら絶対に治ると思い込み、良い結果が得られなかったときに大きなショックを与えるリスクがあります。具体的なNG表現例は以下のとおりです。
- 「日本一の△△専門医が在籍」
- 「どんな症状でも必ず改善させます」
- 「副作用の心配は一切ありません」
- 「100%安全な手術です」
No.1といった最上級のものや、必ずといった断定的なものは、根拠がなければ誇大広告とみなされやすいです。あくまでも公平な事例に基づいた見せ方を心掛けましょう。
比較優良広告
比較優良広告とは、他の病院やクリニックと比較して自分たちが優れている、あるいは有利であるように示す広告です。
禁止される理由は、根拠のない比べ方によって、患者さんが病院を公平に選ぶ障害になるからです。特定の病院を不当におとしめるのは、公正と言えません。具体的なNG表現例は以下のとおりです。
- 「〇〇病院よりも優れた実績があります」
- 「△△クリニックの治療法より評判が良いです」
- 「他のどの病院よりも優れた専門医が揃っています」
特定の病院名を挙げ、誹謗中傷するような見せ方は避けましょう。また、特定の側面だけを切り取って有利に見せるような対比も、誤解を招きやすくなります。
他院との優劣ではなく、独自の価値や特徴を伝えることで患者さんからの信頼を得やすくなります。
未承認医療機器等の広告
日本の薬機法において承認・認証を受けていない医薬品や医療機器を紹介する広告も、禁止されています。国によっては安全が確認されていない治療法に患者さんが手を出さないよう、守ることで信頼を獲得しましょう。具体的なNG表現例は以下のとおりです。
- 「海外で話題の最新〇〇薬による治療を開始しました」(国内未承認の事例)
- 「独自の未承認△△機器で、画期的な変化を体感」
- 自由診療で用いる未承認医薬品の効能をうたう(限定解除要件を満たさない)
自由診療において、未承認の医薬品や医療機器を用いること自体が駄目なわけではありません。しかし、広告する際には厳しいルールがあります。
載せるときは、入手経路、国内・海外で承認されているか否か、副作用といった詳細な情報の明記が必要です。
治療内容に関する広告
治療方法やその効能について、患者さんを誤認させる情報や、根拠に基づかない情報は差し止めされています。広告の情報を鵜呑みにして、自分に合わない治療を受けるのを防ぐためです。具体的なNG表現例は以下のとおりです。
- 「〇〇治療なら、副作用の心配はありません」
- 「たった1回の通院で、長年の悩みが完全に解消します」
- 「最新の△△療法で、驚くほどの若返り!」
- 「当院独自の〇〇術なら、痛みは全くありません」
治療の結果には個人差があります。無視して誰にでも同じ効果があると伝えると、患者さんに誤った期待を抱かせるため危険です。患者さんの体験談や、過剰なBefore/After写真も禁制の事項に抵触しやすい例といえます。
常に患者さんの視点に立った、誤解を与えない言葉選びが大事です。
目を引く病院広告デザインの秘訣4つ

ここでは、記憶に残る広告を作成する4つの秘訣をお教えします。
医療広告ガイドラインを守りながら、患者さんの心に響き、行動を促すような広告を作りましょう。
デザインの基本原則
目を引く病院広告デザインではじめに覚えておきたいのは、デザインの4つの基本原則です。
- 清潔感:清潔で誠実な印象を目指す
- 視認性:誰にでもすぐに読み取れるように配置する
- 情報の整理:情報の優先順位をつける
- 一貫性(トンマナの統一):構成する要素に一貫性を持たせる
チラシやポスター、ホームページなど、どの媒体でも色使いやフォント、写真の雰囲気を統一することで、病院のブランドイメージが定着しやすくなり信頼性も高まります。
デザインの4つの基本原則を押さえることで、見る人に伝わりやすく、印象に残る広告デザインができるでしょう。
配色とフォント
配色とフォントは、病院広告の第一印象を左右する重要な要素です。まず配色は、「ベースカラー」「メインカラー」「アクセントカラー」の3つを意識しましょう。
ベースカラーには白や淡いベージュを使うと、清潔感や安心感を与えられます。メインカラーには自然な印象の緑や温かみのあるオレンジなど、病院のロゴや印象を表す色を選びましょう。アクセントカラーは、電話番号や重要な情報の強調に使うため、全体の5〜10%に抑えるとバランスが整うでしょう。
フォント選びも大切です。読みやすさや誠実さを意識し、奇抜すぎる書体は避けてください。ゴシック体は親しみや力強さを、明朝体は知的で落ち着いた印象を与えます。フォントの種類は2〜3種類に絞り、広告全体で統一感を保つとプロらしい仕上がりになります。
病院のイメージやターゲット層に合わせて、適切な組み合わせを選びましょう。
写真・イラストを効果的に活用する
写真やイラストは、文字だけでは伝わりにくい病院の雰囲気や情報を視覚的に伝えられます。載せる写真は、明るい診察室や最新の設備などのものがおすすめです。
選ぶポイントは、高画質であることです。粗さや暗さが目立つとイメージダウンになります。患者さんの写真を引用する場合は、著作権・肖像権の侵害になるため、事前に許可をもらってください。
広告に合った写真やイラストは、広告の説得力を高め、患者さんの共感を呼びます。素材選びと使い方には細心の注意を払いましょう。
ターゲットに響くキャッチコピーを考える
内容への興味を引くのがキャッチコピーです。どんなに優れた内容でも、キャッチコピーが魅力的でなければ、離脱されかねません。以下の6つを意識してキャッチコピーを考えてみましょう。
- 誰に伝えたいか(ターゲットの明確化)
- 何を一番伝えたいか
- 共感を呼ぶ言葉を選ぶ
- 具体的なメリットを提示する
- 簡潔さ
- わかりやすさ
広告を見るのはどんな人かをイメージし、病院の強みや患者さんへのメリットで最も伝えたいメッセージを探ります。「~でお悩みではありませんか?」といった問いかけや共感の言葉は有効です。
メリットは「〇〇科専門医による丁寧な診療」「駅から徒歩〇分、土日も診療」など、患者さんがわかりやすい言葉で伝えましょう。文も長すぎず、覚えやすいものを選ぶと印象がぐっと上がります。
なお、広告デザインのコツを詳しく知りたい方は、こちらの記事を参照してください。
病院広告で費用対効果の高い媒体2つ

ここでは多くの病院で活用されている媒体としてWeb広告と紙媒体の2つを取り上げ、その理由と活用法を解説します。
Web広告
Web広告は、現代の病院広告において最も費用対効果の高い媒体の一つです。インターネット検索が主流となった今、Web上での露出は認知のために重要です。
Google広告などを活用すれば、年齢・性別・関心に応じたターゲティングが可能で、無駄の少ない集患ができます。アクセス数やクリック数を数値で把握できるため、結果を分析しながら改善できる点も大きなメリットです。
特に有効な手法には、検索結果や地図で上位表示を目指すSEO・MEO対策があります。効果的な対策を行うことで、広告費をかけずに持続的な集客が見込めます。
「〇〇市 内科」などのキーワード検索に連動して表示されるリスティング広告では、意欲の高いユーザーに直接アプローチが可能です。クリック課金型でコスト管理もしやすいのも特徴です。
また病院のホームページ(オウンドメディア)を整備し、情報発信の拠点として活用することで、信頼獲得と長期的な関係構築が可能になります。
紙媒体
紙媒体は、地域密着型の病院にとって費用対効果の高い広告手段のひとつです。チラシのポスティングや新聞折込では、病院の商圏内に住む住民へ直接情報を届けられます。
紙媒体は、Web広告よりも地域に根付いた印象を持ってもらいやすいのがメリットです。高齢者など、インターネットを使わない層にも確実にアプローチできる点も魅力です。
さらに配布エリアを絞ることで無駄を減らすことで、ターゲットに集中した広告が可能です。フリーペーパーや地域広報誌に掲載すれば、多くの住民の目に触れる機会が生まれ認知度の向上も狙えます。
院内の案内パンフレットは、診療内容や専門性を深く伝える手段としても有効です。即効性よりも信頼と浸透を重視したい病院におすすめの媒体です。
Web広告と紙媒体の効果や費用対効果を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
医療広告ガイドライン違反を防ぐためにすること
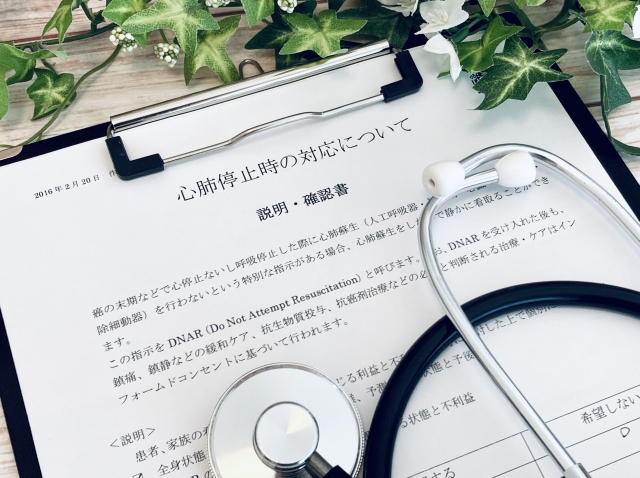
ここでは、違反を未然に防ぐために取り組むべき具体的な対策を4つ紹介します。
病院広告の掲載前チェックリスト
思い込みや見落としを防ぐためのチェックリストは次のとおりです。
【チェック項目例】
- □ 広告の目的は明確か?(誘引性)
- □ 病院名や連絡先は明記されているか?(特定性)
(上記2点がYESなら、ガイドラインの対象となる広告です) - □ 虚偽の内容は含まれていないか?
- □ 誇大な表現はないか?
- □ 患者さんの主観的な体験談を掲載していないか?
- □ 自由診療に関する広告の場合、必要な情報(未承認である旨、費用、リスク等)は明記されているか?
- □ 品位を損ねる表現や、不安を過剰に煽る表現はないか?
- □ 厚生労働省や関連学会が示す最新のガイドラインやQ&Aの題材と照らし合わせて問題ないか?
構成やメディアに合わせてチェックリストを作成・更新しておくとよいでしょう。
社内チェック体制の構築
担当者だけの判断に頼るのは危険です。リスクを低減するためには、組織でチェックする体制が欠かせません。担当者のほか上司や関連部署と連携して、ダブルチェックをすることでフォローしましょう。最終的に決定する責任者を決めておくことも忘れないでください。
また、一度作ったとはいえ、ガイドラインは改正されることもあります。最新の情報を学び、知識をアップデートする機会を設けましょう。
専門家への相談
社内でのチェックだけでは決断に迷う場合、外部の専門家への相談がおすすめです。弁護士であれば、法的な観点から、表現のリスクや違法性についてアドバイスをもらえます。
広告代理店は、ガイドラインに精通し、数多くの制作・実績を持つエキスパートです。ガイドラインを遵守した、効果的な戦略を立案してくれます。
専門家への相談には費用が必要です。しかし、誤った認識で進める前に外からの意見を聞くことはベストでしょう。
掲載後の見直し
広告は掲載・公開したら終わりではなく、掲載後の継続的な見直しが大事です。掲載した情報が古くなっていないか、規制されていないか確認しましょう。患者さんや行政から広告に関する指摘を受ける可能性もゼロではありません。
指摘を受けたときは、真摯に受け止め、速やかに対応する姿勢が大切です。
まとめ:病院広告を駆使して集患をしよう

病院広告で最も重要なのは、医療広告ガイドラインを正しく理解し、規約を守ることです。誇大広告や比較優良広告などを避け、客観的な事実に基づいた誠実な情報発信を心掛けましょう。
同時に、読者を意識し構想やキャッチコピー、Web広告や紙媒体の特性を活かした戦略的アプローチも欠かせません。掲載前のチェックを欠かさず徹底することで、安心して広告活動を継続できます。
病院広告は、患者さんとの大切なコミュニケーション手段です。この記事で得た知識を活かし、地域への貢献と病院の発展につなげていきましょう。