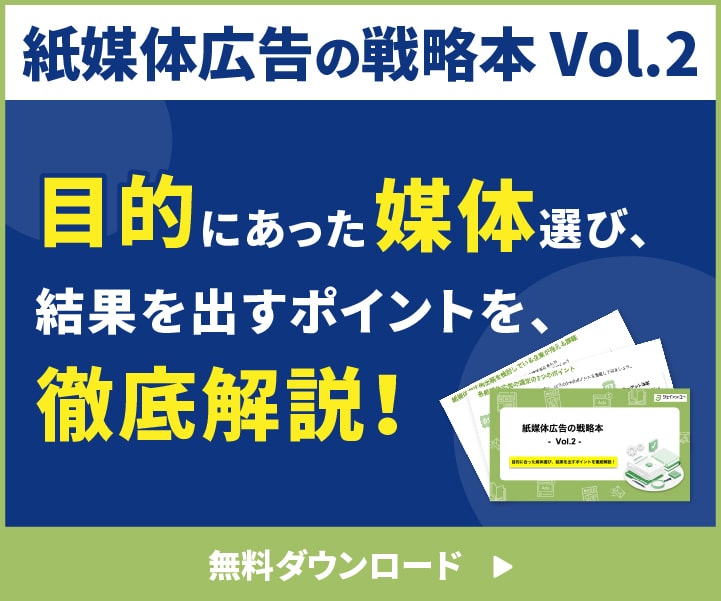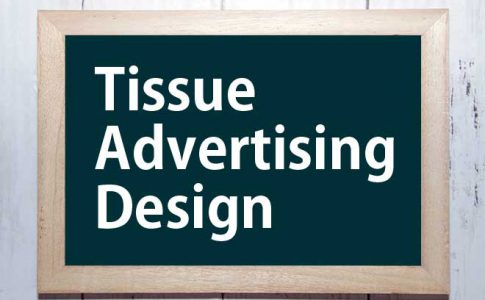「地元のビジネスをもっと多くの人に知ってもらいたいけど、どんな広告手法を選べばいいのだろう?」
地域密着型の広告手法として、バス広告が注目を集めています。
通勤・通学や買い物などで多くの方が利用するバスは、日常生活に溶け込んだ広告媒体として絶大な効果を発揮します。
しかし、バス広告にはどんな種類があり、どう選べばよいのか迷う方は多いでしょう。
この記事では、バス広告の基礎知識や5つの広告種類、メリット・デメリット、選び方の手順などを詳しく解説します。
地域の特性を生かした効果的なマーケティング手法として、バス広告の可能性を探ってみましょう。
また弊社では、Web広告で思うような効果を得られない方に向けて「紙媒体広告の効果的な活用法」を紹介しています。
詳しく知りたい方は、ぜひバナーをクリックして資料をダウンロードしてください。
目次
バス広告とは?

バス広告とはバスの車体や車内を活用した広告手法で、地域住民への認知度向上や企業イメージの向上に効果的な交通広告の一種です。
バスは日常的に地域住民の目に触れる機会が多いため、広告の訴求力が高まります。通勤・通学や買い物の際に繰り返し目にすることで、ブランドやサービスも自然と認知されやすくなります。
例えば、地元の飲食店やクリニックがバス広告を活用すれば、近隣住民に効果的にアプローチでき新規顧客の獲得ができるでしょう。イベント告知として短期間の掲載も可能で、地域密着型の情報発信にも適しています。
バス広告は、地域に根ざした広告手法として高い認知効果を発揮するため、企業のブランド価値向上にもつながる優れたマーケティング手法です。
交通広告について知りたい方は、以下の記事あわせても参考にしてください。
バス広告の種類5選

バス広告は地域密着型のマーケティング手法として、さまざまな形で利用されています。
ここでは、代表的な5つのバス広告の種類を紹介します。
窓上ポスター広告
窓上ポスター広告はバス車内に設置される広告で、乗客が座席に着いた際に自然と目に入る位置に掲示されます。
通勤・通学などで長時間バスを利用する乗客には、繰り返し視認されやすい点が特徴です。バス内は限られた空間のため、他の広告に埋もれにくく高い訴求力を発揮します。
商品やサービスの認知拡大だけでなく、イベント告知や地域密着型のPRにも適した広告手法です。
窓ステッカー
窓ステッカーはバスの窓に貼られる広告で、乗客だけでなくバスの外を歩く人々にもアプローチできる点が特徴です。
視認性が高く信号待ちや停車中に注目を集めやすいため、ブランドの認知度向上に効果的です。
デザイン次第でインパクトのある広告展開が可能で、商品やサービスの魅力を視覚的に強調できます。
企業のブランディングやキャンペーン告知にも適しており、幅広い用途で活用できるでしょう。
運転席後部広告
運転席後部広告は運転席の背面に設置される広告で、バスの乗客が自然と目にする位置に掲示されます。
座席に座った乗客の視線が集まりやすく、高い訴求効果が期待できます。
バスの移動時間が長いほど広告を目にする機会が増え、メッセージが記憶に残りやすいのが特徴です。
運転席後部広告は詳細な情報を掲載できるため、購買意欲を高めるのに有効です。
車体ラッピング
車体ラッピングはバスの外装全体を広告として活用する手法で、大きな視覚的インパクトを与えられるのが特徴です。
バスが走行するたびに広範囲のエリアで広告を露出できるため、地域に密着しながらも高い広告効果を発揮します。
ブランドの認知度向上や新商品のプロモーションに適しており、鮮やかなデザインやキャッチコピーを用いることで強い印象を残せます。
街中を移動する広告として、視認性と訴求力を兼ね備えた効果的な手法です。
車内アナウンス
車内アナウンスは、バスの運行中に車内放送を利用して広告を流す手法です。
視覚的な広告とは異なり音声で直接メッセージを届けるため、注目を集めやすく印象に残りやすいのが特徴です。
地域イベントや店舗のプロモーションに適しており、ターゲット層にダイレクトに訴求できます。
他の広告と組み合わせることでより効果的なマーケティング戦略を展開できるため、目的に応じた活用が成功の鍵となるでしょう。
なお、バス広告と同じく地域に根ざした広告の一つ「駅貼り広告」について知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
バス広告のメリット5つ

バス広告は地域密着型の広告手法として多くの企業から注目されています。
以下では、バス広告の5つの主なメリットを詳しく解説します。
地域密着型の広告ができる
バス広告は特定の地域に密着した広告展開が可能で、地元住民に効果的にアプローチできます。
バスは決まったルートを繰り返し走行するため、地域の人々の目に触れる機会が多く親しみやすい印象を与えられます。
例えば、地元の飲食店やクリニックがバス広告を活用すれば、通勤・通学者や買い物客に向けて自然に店舗情報を届けられます。
短期間の掲出ができる
バス広告は短期間の掲載が可能で、季節限定のプロモーションやイベント告知に適した広告手法です。
掲載期間を柔軟に設定できるため、必要なタイミングで効果的に情報を発信できます。
期間限定のキャンペーンや新商品の発売告知をバス広告で行えば、ターゲット層に短期間で広く認知させることが可能です。
プロモーションの目的に合わせた短期間の広告を出すならバス広告がおすすめです。
広いターゲット層にリーチできる
バスは日常的に多くの人が利用するため、バス広告は通勤・通学者や買い物客、高齢者など幅広いターゲット層にアプローチできます。
地域のスーパーがバス広告を活用すれば、日常的に買い物をする主婦層や高齢者に効果的に訴求できます。学習塾の広告なら通学中の学生やその親の目に留まりやすく、集客につながる可能性があるでしょう。
バス広告は特定の層に限らず、幅広い年代や属性の人々に向けたマーケティングが可能なため、さまざまなビジネスに適した広告手法です。
繰り返しアプローチできる
バス広告は同じルートを繰り返し運行するため、メッセージが自然に記憶へ刻まれやすいのが魅力です。
地元のフィットネスクラブがバス広告を活用すれば、毎日バスを利用する通勤・通学者に継続的にアプローチできるため、「気になっていたので試してみよう」という行動喚起につながる可能性が高まります。
バス広告はターゲットに継続して訴求できるため、ブランド認知度の向上や購買意欲の促進に効果的です。
企業やサービスの信頼性UPにつながる
バス広告は公共交通機関に掲示されることで多くの人に親しみやすいイメージを与え、企業やサービスの信頼性向上につながります。
地元の金融機関や医療機関がバス広告を活用すれば、「地域に根差した安心できる企業」として認識されやすくなります。
バス広告は公的な交通機関の一部として扱われるため、信頼性の高い広告媒体としての印象を持たれやすいでしょう。
バス広告は企業のブランドイメージを向上させ、地域住民の信頼を獲得するのに効果的な広告手法といえます。
バス広告のデメリット3つ

地域に密着した効果的な広告手法として注目されるバス広告ですが、いくつかのデメリットもあります。
ここでは、バス広告の代表的なデメリットを3つ解説します。
印象的な広告が難しい
バス広告は掲示スペースが限られているため、他の広告媒体と比べて印象的なデザインを作るのが困難です。
車体ラッピング広告ではバスの形状に合わせたデザインが必要となるため、窓やドアの配置を考慮しなければなりません。適切なレイアウトでなければ広告のメッセージが伝わりにくくなる可能性があります。
バス広告を効果的に活用するには、高いデザインスキルと視認性を意識した工夫が必要です。
効果測定が難しい
バス広告はデジタル広告と比べて効果測定が難しく、広告の成果を正確に把握しにくいです。
バス広告の場合、「広告を見た方が実際にどの程度行動を起こしたのか」直接的なデータを取得するのが困難です。
バス広告を見た方が店舗を訪れたりサービスを利用したりしても、それが広告の影響によるものかを判断するのは難しくなるでしょう。
広範囲への広告が難しい
バス広告は特定の路線や地域に限定されるため、広範囲での広告展開が困難です。
地方のバス路線では利用者が少なく、広告を目にする人の数も限られます。結果ターゲット層に十分アプローチできず、期待する広告効果が得られない可能性があります。
バス広告は地域密着型の強みがある一方で、広範囲に情報を届けたい場合は他の広告媒体と併用するなどの工夫が必要です。
バス広告の料金

バス広告の料金は、広告の種類や掲載期間、地域などによって大きく変動します。
ここでは、広告掲出費やデザイン費、制作費・取付作業費の3つにわけて、それぞれの費用について詳しく解説します。
広告掲出費
バス広告の掲出費用は、広告の種類や掲載期間、バスの運行ルートによって異なります。
以下の表に主な広告タイプとその費用目安をまとめました。
| 広告種類 | 掲出期間 | 費用目安 | 特徴・ポイント |
| フルラッピング広告 | 1ヶ月〜 | 40万円〜/月、年間400万円〜 | バス全体を覆うため視認性が高い |
| パートラッピング広告 | 1ヶ月〜 | 10万円〜/月 | 部分的なラッピングで比較的安価 |
| 車内ポスター | 1ヶ月〜 | 数万円〜 | 乗客の目に留まりやすい |
| 車内アナウンス | 年間契約 | 10万円未満〜200万円 | 音声で直接訴求できる |
バス広告は種類ごとに費用が異なるため、目的や予算に応じた選択が重要です。
デザイン費
バス広告のデザイン費は広告制作にかかる費用で、効果的な広告展開には欠かせない要素です。
バス広告は特殊な形状や視認性を考慮する必要があるため、交通広告専門のデザイナーが担当することが一般的です。
以下に主なバス広告のデザイン費用目安をまとめました。
| 広告種類 | デザイン費用目安 | 特徴・ポイント |
| フルラッピング広告 | 20万円〜50万円 | バスの形状に合わせた複雑なデザインが必要 |
| パートラッピング広告 | 10万円〜30万円 | 部分的なデザインで比較的安価 |
| 車内ポスター | 3万円〜10万円 | シンプルな構成でデザインしやすい |
| 車内アナウンス | なし(音声制作費別途) | 視覚的デザインは不要 (音声収録日が発生する場合あり) |
フルラッピング広告ではバスの形状に合わせたデザインが求められるため、制作費が高くなる傾向があります。一方、シンプルなデザインの車内ポスターであれば比較的安価に抑えられます。
制作費・取付作業費
バス広告の制作費・取付作業費は、広告を制作しバスに取り付けるためにかかる費用です。
広告のサイズや素材、施工の難易度によって費用が変動するため、事前に確認することが重要です。
以下に、主なバス広告の制作費・取付作業費の目安をまとめました。
| 広告種類 | 制作費・取付作業費目安 | 特徴・ポイント |
| フルラッピング広告 | 50万円〜150万円 | 大型シートを使用し、施工コストが高い |
| パートラッピング広告 | 20万円〜50万円 | 部分的な施工で比較的安価 |
| 窓ステッカー | 5万円〜20万円 | 窓の大きさや枚数により変動 |
| 車内ポスター | 1万円〜5万円 | 低コストで簡単に設置可能 |
施工業者によって料金が異なるため、複数の見積もりを取ることで適正価格を把握しましょう。
なお、媒体別の広告費を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
バス広告を選ぶ手順3ステップ

バス広告を効果的に活用するためには選び方が重要です。
ここでは、バス広告を選ぶ際の3つのステップを解説します。
ステップ1:ターゲットを明確にする
バス広告を成功させるには、まずターゲットを明確にすることが重要です。
ターゲットが明確であれば適切なバス路線や広告デザインを選びやすくなるため、広告効果を最大化できます。
学生向けのサービスを宣伝する場合は、学校や大学周辺を運行するバス路線を選ぶといいでしょう。
シニア層を対象とする場合は高齢者が多く利用する路線を選び、見やすいフォントや分かりやすいメッセージを用いることで訴求力を高めることが可能です。
ターゲットを明確にすることで、より効果的な広告戦略を立てられバス広告の成功率を高めることにつながります。
ステップ2:バス広告を掲出する目的を決める
バス広告を効果的に運用するには、掲出する目的を明確にすることが重要です。
目的を決めることでターゲットに適切なメッセージを伝えやすくなるため、具体的な広告戦略を立てやすくなります。
新規店舗のオープンを告知する場合は、店舗の場所やオープン日を強調したデザインにすることで認知度向上に効果的です。目立つカラーや大きな文字を使うことで、短時間でも情報が伝わりやすくなります。
一方、求人募集が目的であれば、働きやすさや待遇を前面に出した広告内容にすることで、求職者の興味を引き応募につながりやすくなります。
バス広告の目的を明確にすることで、広告のデザインや掲出期間を最適化できるため、より効果的なバス広告の運用ができるでしょう。
ステップ3:設置場所などからバス広告を選ぶ
ターゲットと広告の目的が決まったら、最適なバス広告の種類と設置場所を選ぶことが重要です。
適切な広告形式を選択することで、より高い効果が期待できます。
広範囲にリーチしたい場合、バス全体を広告として活用できる車体ラッピングが効果的です。移動することで多くの人の目に触れるため、ブランドの認知度向上につながります。
一方、地域密着型の広告を狙うなら、特定の路線や停留所など地元住民の目に触れる機会を増やすことで、より効率的に訴求できるでしょう。
ターゲット層や目的に応じて広告の種類や掲出場所を決めることで、効果的なバス広告の展開が可能になります。
バス広告を掲出する際のポイント

バス広告を効果的に掲出するためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、バス広告を実施する際に必ず注意しておきたいポイントを2つ紹介します。
景観を損なわない広告デザインにする
バス広告は移動する媒体であるため、周囲の景観に配慮したデザインにする必要があります。
地域に溶け込むデザインを意識することで、住民からの好感度が高まるため広告が受け入れられやすくなります。
景観を損なわないデザインのポイントは以下のとおりです。
- 色やデザインを地域の景観と調和させる
- 派手すぎず見やすいデザインを心掛ける
- 公共の場にふさわしい内容を選ぶ
景観を意識したデザインを取り入れることで、地域の人々に受け入れられやすいバス広告を展開しましょう。
バス広告をデザインする際のポイントを知りたい方は、次の記事もあわせて参考にしてください。
バス会社で設けられた規定を守る
バス広告を掲出する際には、各バス会社が定める規定を遵守することが不可欠です。
バス広告の規定を守るポイントは次のとおりです。
- 広告のサイズや位置、掲出期間を確認する
- 使用可能な色やフォントの制限を確認する
- デザイン案を事前に提出し、審査を受ける
事前にルールを確認し適切に対応することで、スムーズな広告掲出が可能になります。
まとめ:自社に適したバス広告で効果的なマーケティングを実施しよう!

バス広告は地域密着型の広告展開が可能で、幅広いターゲット層にリーチできる強力なマーケティング手法の一つです。
短期間の掲出ができたり繰り返し視認されたりすることで、認知度向上に貢献する点が大きなメリットです。
一方で、印象的な広告を作る難しさや効果測定の困難さといった課題もあります。景観との調和を意識したデザインや、バス会社の規定を遵守することも欠かせません。
バス広告を活用する際は、自社の目的やターゲットに合った種類の広告を選択することが成功の鍵となるでしょう。
また弊社では、Web広告で思うような効果を得られない方に向けて「紙媒体広告の効果的な活用法」を紹介しています。
詳しく知りたい方は、ぜひバナーをクリックして資料をダウンロードしてください。