「この広告、本当に出して大丈夫だろうか」
健康食品の広告を出そうと考えたとき、多くの方がこうした不安を抱えるでしょう。
特に通販では広告が集客の要になる一方、薬機法や景品表示法、健康増進法など、守るべきルールが多く存在します。
うっかり違反してしまうと、行政指導や販売停止などのリスクも避けられません。
そこで本記事では、健康食品の通販におすすめの広告媒体7選を紹介しながら、それぞれの特徴やメリットを解説します。
また、広告表現でやってはいけないNG表現や、注意すべき法律のポイントについてもわかりやすくお伝えします。
安全かつ効果的な広告運用のために、ぜひ参考にしてください。
また弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。
詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。
健康食品の通販におすすめの広告媒体7選
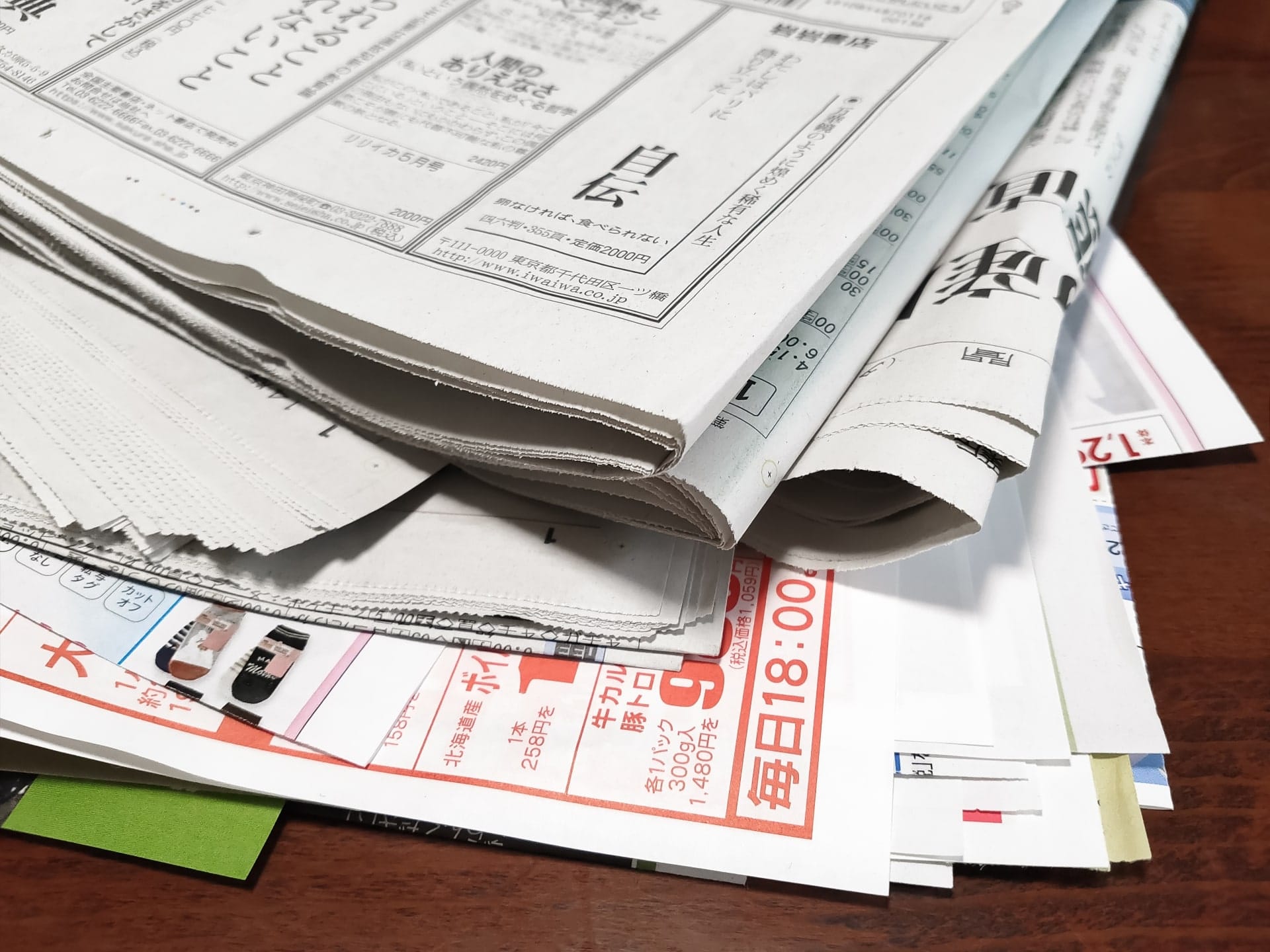 健康食品の通販で広告を使って集客するには、次の7つの方法が有効です。
健康食品の通販で広告を使って集客するには、次の7つの方法が有効です。
- チラシ
- 新聞広告
- 雑誌広告
- フリーペーパー
- テレビCM
- SNS
- リスティング広告
それぞれの方法を詳しく解説します。
①チラシ
健康食品の通販で集客を狙う方法として、チラシは非常に効果的です。
チラシの配布方法には、新聞折込と単独で配布するポスティングの2種類があります。
いずれの方法でもチラシが手元に残るため、すぐに注文しなくても後日あらためて購入につながる可能性があるのが大きな強みです。
折込チラシ
新聞と一緒に配布される折込チラシは、新聞を購読している家庭へ確実に届けられる広告手法です。
新聞購読者の多くは50代以上の中高年層であり、健康や生活習慣への意識が高い世代といえます。
そのため、健康食品のターゲット層と重なりやすく、非常に相性の良い媒体です。
狙いたい年代に効率的に訴求できる点が、折込チラシの大きな魅力です。
ポスティング
健康食品の通販で、幅広い世代や比較的若い層にアプローチしたい場合には、ポスティングによるチラシ配布が効果的です。
ポスティングであれば新聞を購読していない家庭にもチラシが届くため、新聞未購読世帯が増えている現在では、特に若年層への訴求に向いています。
また、配布エリアを細かく指定できるため、ターゲットを絞った展開が可能です。繰り返し同じエリアに配布することで、地域内での認知度を高める効果も期待できます。
店舗を持ちながら健康食品の通販を行っている場合には、店舗集客と通販の両面でメリットを得られる手法といえるでしょう。
チラシについてさらに知りたい方は、「チラシのポスティングは集客できる?反響率や業者の選び方を紹介」も参考になるためぜひご覧ください。
②新聞広告
健康食品を購入する層に向けて広告を出すのであれば、新聞の広告欄を活用するのも効果的です。
新聞購読者の特徴としては、年齢層が高めで、比較的所得が高いことがあげられます。
公益財団法人 新聞通信調査会の「第13回メディアに関する全国世論調査(2020年)」によると、60代以上の約80%が新聞を購読しているというデータがあります。
こうした層は健康意識が高く、信頼性のある情報を重視する傾向があるため、新聞広告との相性は抜群です。
掲載する際は、読み手の目に留まりやすいレイアウトやキャッチコピーを意識することで、ライバルと差別化できます。
新聞広告のデザインに悩む場合は、「新聞広告デザインは誠実さやインパクトでユーザーをつかむ!」を参考にしてみてください。
③雑誌広告
雑誌はジャンルごとにターゲットが明確に設定されているため、健康食品の広告との相性が良い媒体です。
たとえば、50代~60代の主婦層は健康や美容に対する関心が高く、体調管理や肌の悩みに対応する健康食品との相性は良いでしょう。
また20代〜40代女性向けのファッション誌では仕事や家事で疲れを感じやすい年代に向け、リフレッシュや美容を意識した健康食品を訴求することで、高い反応が得られる可能性があります。
また、雑誌はお金を払って購入するため、一定の期間保管しておく人が多いです。
手元にある雑誌を繰り返し読むことで、同じように広告にも目を通してもらえます。
何度も顧客の目に触れることで、単純接触効果が期待できるでしょう。
広告を出すことで得やすい効果については「紙広告で効果を得るには?効果測定の方法もあわせてご紹介」で詳しく解説しています。
④フリーペーパー
フリーペーパーとは、無料で配布されている冊子のことで、健康食品の広告媒体としても活用されています。
フリーペーパーにはさまざまなジャンルがあり、たとえば以下のような情報誌があります。
- 地域情報誌
- 美容系情報誌
- 生活情報誌
- 育児情報誌
- 健康・シニア向け情報誌 など
ターゲットとなるユーザー層に応じて、掲載する媒体を選ぶことで、健康意識の高い読者層に効率良く訴求することが可能です。
掲載費用が比較的安価である点もメリットの一つです。
また駅や病院、コンビニなどで気軽に手に取ってもらえるため、有料の雑誌よりも多くの人の目に触れる可能性があります。
冊子形式であることから一定期間保管されやすく、掲載後も継続的な反響が期待できます。
ただし、フリーペーパーは手に取ってもらえなければ広告が見られないのが弱点です。
そのため、継続的な出稿や読者の関心を引くデザイン・見出しが重要になります。
ぜひ「フリーペーパーでの広告効果を高めるポイントは?メリットを紹介!」で、効果的な配布方法と広告を出すうえでのメリットとデメリットをご覧ください。
⑤テレビCM
テレビCMは、健康食品の通販においても高い集客効果が期待できる広告手法です。
健康食品は効果的な摂取方法や継続の重要性など、ある程度の説明を必要とする商品であるため、映像と音声を使って情報を伝えられるテレビCMとの相性は非常に良好です。
以下のような内容を映像の中で丁寧にアピールすることで、視聴者に安心感や信頼感を与えられます。
- 実際に使用している人の声(口コミ・体験談)
- 製品の特徴や健康への働きかけ(ただし薬機法に配慮)
- 原材料や製造工程の安全性
- 飲みやすさ・続けやすさ
- 毎日の継続が健康維持につながること
テレビCMは放送エリアや放映時間帯によってターゲットをある程度絞れるため、年齢層や生活リズムに合わせた訴求が可能です。
認知拡大と購買行動の促進を同時に狙える媒体といえるでしょう。
テレビCMはマス広告と呼ばれる広告のひとつです。
「マス広告とは?4つの媒体の特徴やオンライン広告との違い」でテレビCMを含むマス広告のメリットも解説しているため、ぜひご覧ください。
⑥SNS
健康食品の通販でも、SNSは非常に有効な集客手段のひとつです。
SNSは他の広告媒体に比べてユーザーとの距離が近く、双方向のコミュニケーションが取れる点が大きな特徴です。
最近では、Web検索よりもSNSで評判や口コミを調べてから購入を検討するユーザーが増えており、SNS上のリアルな声が健康食品の購入意欲や信頼性に大きな影響を与えています。
有料広告を出稿できる主なSNSには以下の5つがあります。
- X(旧Twitter)
- YouTube
- TikTok
これらのSNSでは性別・年齢・地域・関心ジャンルなどの属性に基づき、広告の配信ターゲットを細かく設定することが可能です。
そのため「美容に関心のある30代女性」や「生活習慣が気になる50代男性」など、特定の健康課題を抱える層にピンポイントで訴求できる点が大きなメリットです。
口コミやレビューと組み合わせることで、信頼性の高いプロモーションが実現できます。
⑦リスティング広告
リスティング広告とは、Yahoo!JAPANやGoogleなどの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、検索結果の上部に表示される広告のことを指します。
健康食品を探しているユーザーが検索するキーワードに連動して広告が表示されるため、すでに関心を持っている層に直接アプローチできるという点が大きなメリットです。
また、SEOによって上位表示されているサイトよりもさらに目立つ位置に表示されるため、クリック率も高くなるでしょう。
広告掲載はオークション形式で行われ、「1クリックあたり◯円」という形でキーワードに入札し、検索結果画面に広告を表示させます。
たとえば「ダイエット サプリメント」というキーワードに対して150円の上限クリック単価を設定した場合、競合他社が200円で入札していれば自社広告よりもそちらが優先的に表示されます。
なお、表示順位は金額だけでなく、広告の品質スコアなども関係するため注意が必要です。
ただし健康食品の分野は競合が多く、人気キーワードではクリック単価が高騰する傾向があります。
やみくもに入札すると広告費がかさみ、かえって赤字になるリスクもあるため、適切なキーワード選定と費用対効果の分析が欠かせません。
健康食品の広告では規制を守ることが重要

健康食品の広告には、消費者を誤認させないための法律が複数存在します。
法令に違反すると、行政処分や信頼の低下を招くリスクがあるため、十分な注意が必要です。
景品表示法とは
景品表示法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、公正な取引を確保するための法律です。
健康食品の広告においては、実際以上に効果があるように見せる「優良誤認」や、他社商品より著しく優れているように見せる「有利誤認」などが問題となります。
たとえば、「飲むだけで10kg痩せる」などの表現は、根拠がない限り違法とされる可能性があります。
表示内容には科学的な裏付けが求められるため、誤解を招くような過大表現は避けなければなりません。
健全な広告を行うためにも、表示内容のチェックは欠かせません。
薬機法とは
薬機法(旧・薬事法)は、医薬品や医療機器、化粧品、そして医薬部外品などの品質や安全性を確保するための法律です。
健康食品は医薬品ではないため、「治る」「予防できる」などの医療的な効能をうたうことは認められていません。
たとえば「高血圧が改善する」「がんが治る」といった表現は、薬機法違反となるおそれがあります。
誇大広告や誤認を招く記載は処分の対象となるため、慎重な表現が求められます。
効果を連想させる文言でも、医薬品と誤解される内容には注意が必要です。
健康増進法とは
健康増進法は、国民の健康を保持・増進することを目的とした法律で、食品の表示や広告についても一定の制限があります。
そのため科学的根拠のない効果をうたったり、誤解を与える表現を使ったりすることは禁止です。
たとえば「誰でも確実に痩せる」といった断定的な表現は、消費者を誤認させるおそれがあるため問題となります。
消費者の健康被害を未然に防ぐという観点からも、適正な情報提供が求められます。
健康食品の広告におけるNG表現例

健康食品の広告では、使ってはいけない表現が明確に定められています。
違反すると行政指導や掲載停止の対象になるため、事前に把握しておかなければなりません。
以下では、代表的なNG表現を紹介します。
効果・効用
健康食品の広告では、「○○に効く」「△△を改善する」など、明確な効果や効用をうたう表現は基本的に禁止されています。
こうした表現は医薬品にのみ認められており、健康食品で使用すると薬機法違反となる可能性があります。
たとえば「疲労回復に効果的」「血糖値が下がる」といった文言は、科学的根拠があっても認められないケースが多いです。
曖昧な表現であっても、効能を連想させる記載には注意が必要です。
治る・予防する
健康食品の広告で「病気が治る」「発症を防ぐ」といった治療や予防を示す表現は、薬機法により禁止されています。
このような効能は医薬品にしか認められておらず、健康食品では一切使用できません。
たとえば「風邪をひかなくなる」「がんを予防する」といった表現は、明確にNGです。
仮に愛用者の声として紹介する場合であっても、同様の判断をされることがあるため注意が必要です。
誤認を避けるためにも、健康の維持や栄養補助の範囲にとどめた表現を心がけましょう。
用法・用量
健康食品の広告では、「1日3回、食後に3錠」など、医薬品のような用法・用量の記載は認められていません。
この種の表現は、あたかも医薬品と同等の効果があるかのような誤解を与えるため、薬機法上問題となります。
「決められた量を守れば効果がある」といった印象を与える文言も、違反と判断される可能性は少なくありません。
そのため、摂取の目安を伝える際は「1日◯粒を目安に摂取してください」など、あくまで目安であることを強調する必要があります。
適切な表現を心がけることで、消費者との信頼関係を損なわずに商品の訴求ができます。
健康食品の広告表現が不安なら第三者に確認してもらおう
 健康食品の広告には、媒体選びから表現方法まで、守るべきポイントが多く存在します。
健康食品の広告には、媒体選びから表現方法まで、守るべきポイントが多く存在します。
集客効果の高い広告手法を選んでも、法令に違反する内容であれば、逆に信頼を損なう結果になりかねません。
専門知識が求められる分野だからこそ、自社だけで判断せず、薬機法や景品表示法に精通した第三者に事前確認を依頼することが重要です。
外部チェックを受けることで、法的リスクを減らし、安心して広告を展開できます。
安全性と信頼性を両立させた広告づくりを目指しましょう。
弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。
詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。


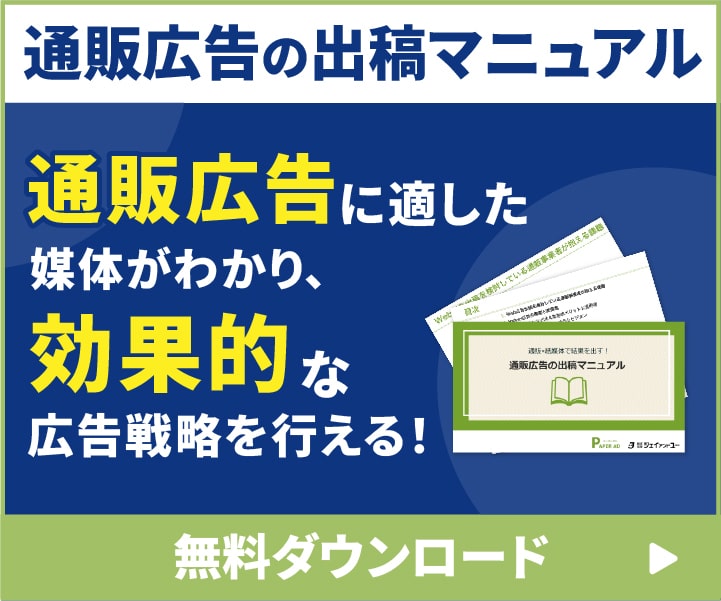








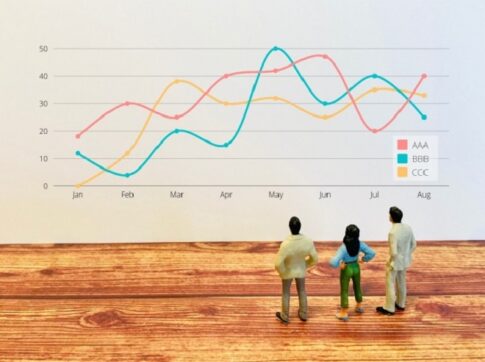

コメントを残す