通販・EC事業において、広告は“経費”ではなく“戦略”です。
競合がひしめく市場では、広告手法の選び方ひとつでCPO(顧客獲得単価)に天と地ほどの差が出ることも少なくありません。
そこで本記事では、オンラインとオフラインそれぞれの広告手法について、特性・活用法・注意点をわかりやすく解説します。
手当たり次第に出稿するのは卒業して、貴社の商品に合ったスマートな広告運用を始めましょう。
広告選定に悩む担当者の方にとって、今日から役立つヒントが詰まっています。
ぜひ最後までお読みください。
また弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。
詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。
目次
通販・EC事業にとって広告戦略が重要な理由

通販・EC事業では、広告戦略の立て方ひとつで、売り上げが大きく変わります。
業界全体の競争が激化し、新規顧客の獲得単価(CPO)は年々上昇しています。
そのため従来と同じ手法・予算では、期待する成果を得にくくなっているのが実情です。
また、広告チャネルも多様化・複雑化しており、媒体ごとの特性や運用難易度の差が大きくなっています。
例えば、オンライン広告ではアルゴリズムやユーザー行動の変化に素早く対応する必要があります。
一方、オフライン広告も再注目されつつあるとはいえ、出稿先を見誤れば費用対効果が下がってしまうでしょう。
つまり、広告は単なる宣伝活動ではなく、“どこに・誰に・どう伝えるか”を精緻に設計する経営判断の一部。
通販・EC事業では、広告戦略そのものが競争力を左右する要因なのです。
今後の通販・EC業界のトレンドについては、以下の記事もご覧ください。
通販・EC事業におけるオフライン・オンライン広告のメリットとデメリット

通販・EC事業の広告施策では、オンライン・オフライン広告の両面を理解し、目的に応じた使い分けが重要です。
本章では、オフライン・オンライン広告それぞれの特徴と利点・注意点を整理します。
オフライン広告のメリット・デメリット
通販・EC事業でも、オフライン広告はターゲティング次第で十分に効果を発揮します。
紙媒体に慣れた層には新聞やチラシ、DMのようなオフライン広告が届きやすく、手元に残る安心感や視認性の高さも魅力です。
信頼感を大事にしたい商材や、高齢層向けのプロモーションで特に力を発揮します。
例えば、健康食品のDMならば封を開けて読んでもらいやすく、商品に対する関心も高まりやすくなるでしょう。
反面、広告費はやや高めで、配布エリアの調整も柔軟とは言えません。
さらに、反応率や費用対効果の測定にも工夫が必要です。
しかし、オンライン広告が届きにくい層へのアプローチ手段として、オフライン広告は今も健在です。
商材やターゲットに合わせて上手に組み合わせましょう。
オンライン広告のメリット・デメリット
オンライン広告は、通販・EC事業で成果を上げるための主力です。
ターゲット設定の自由度が高く、広告の効果も数値で把握しやすいのが特徴です。
小規模な出稿から始められるうえ、調整や改善をスピーディに行える点も、現場目線では大きな利点と言えるでしょう。
例えば、SNS広告ならユーザーの興味関心に応じて表示を制御できるため、関心度の高い層に効率良くアプローチできます。
ただし、競合が多くクリック単価が上がりやすい傾向もあります。
さらに、プラットフォームの仕様変更や広告規制といった外的要因の影響を受けやすいでしょう。
以下に、オンライン・オフライン広告の特徴をまとめましたので、参考にしてください。
| オンライン広告 | オフライン広告 | |
| 主な媒体 | SNS広告、リスティング広告、ディスプレイ広告、動画広告など | 新聞、雑誌、チラシ、DM、テレビ、ポスティングなど |
| メリット | ・高精度なターゲティングが可能 ・効果測定がしやすい ・少額から始められる ・即効性がある | ・高齢者層など紙媒体に強い層に届く ・信頼感やブランド認知の強化に有効 ・物理的なインパクトがある |
| デメリット | ・競合との競争が激しい ・広告単価が変動しやすい ・規制や仕様変更の影響を受けやすい | ・効果測定が難しい ・コストが高くなる傾向 ・ターゲティングの精度に限界がある |
| 向いているケース | ・短期的な販促や新商品のテスト ・若年層 ・購買意欲の高い層へのアプローチ | ・信頼感を重視する商材(例:健康食品・金融系) ・高齢層やロイヤル顧客への継続アプローチ |
また、オンラインとオフラインの融合についても以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひお読みください。
通販・EC事業におすすめのオフライン広告7選

昨今ではオンライン施策に注目が集まりがちですが、オフライン広告も通販・EC事業との相性が良い広告手法です。
特に、高齢層をターゲットにした商材や、信頼感を重視したい分野では、紙媒体やリアル接点が力を発揮します。
本章では、以下の8つのオフライン広告の特徴と、活用時のポイントを紹介します。
- ①新聞広告
- ②雑誌広告
- ③テレビ広告
- ④ダイレクトメール
- ⑤同封・同梱広告
- ⑥店頭配布チラシ・ポスティング
- ⑦フリーペーパー・地域情報誌への掲載
- ⑧交通広告(電車・バス・駅構内)
それでは、順に解説していきましょう。
①新聞広告
新聞広告は、地域密着型のアプローチや高齢層への訴求に適している広告手法です。
特に紙面にしっかり目を通す読者が多い朝刊では、訴求力のあるビジュアルやタイムリーな訴求内容が効果を発揮します。
また、新聞が持つ媒体としての信頼性が、商品への安心感にもつながります。
一方、広告費は高めで、掲載エリアによっては反響にばらつきが出やすいのが難点です。
即効性より、中長期的なブランドづくりやシニア層の掘り起こしといった目的に向いています。
掲載面や曜日を選べば、反応率の底上げも狙えるでしょう。
新聞広告については、以下の記事でも詳しく解説しています。
②雑誌広告
雑誌広告は、読者の関心やライフスタイルが明確なため、ターゲットを絞った広告展開に適しています。
例えば、美容雑誌ならコスメ、育児雑誌ならベビー用品といったように、読者が求めている情報に自然に入り込めるのが魅力です。
読者は情報収集目的で雑誌に目を通すため、広告もじっくり読まれやすい傾向があります。
加えて、誌面のビジュアル訴求力が高く、商品ブランディングにも向いています。
ただし、出稿までに時間がかかる、掲載期間が長くてもレスポンスがすぐには出にくいといったデメリットもあります。
即効性を狙うより、信頼感やブランド認知を高める目的で活用したい手法です。
雑誌広告について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
③テレビ広告
テレビ広告は、圧倒的なリーチ力と信頼性の高さが特長です。
特に全国放送やゴールデンタイムに流すことで、一気に認知拡大を図れます。
タレント起用やストーリー性のあるCMを用いれば、商品への関心や感情的なつながりを生みやすく、ブランディングにも効果的です。
また、通販向けにはインフォマーシャル型の広告も有効で、商品特性や使い方をじっくり紹介できます。
ただし、費用が高く、成果測定もしにくいため、継続出稿や改善施策が難しい点が課題です。
EC事業との相性はやや限定的ですが、話題性を重視したい新商品のプロモーションや、一定の売上規模をもつ企業にとっては大きな武器になるでしょう。
テレビ広告については、以下の記事でも詳しく解説しています。
④ダイレクトメール
ダイレクトメール(DM)は、特定のターゲット層に対して個別に情報を届けられる点が強みです。
紙の質感やデザインで商品イメージを演出しつつ、手元に残る形で情報を届けられるため、信頼性や購買意欲が高まります。
特に定期購入や高単価の商品では、読み物風の構成にして関心を引くアプローチも有効です。
一方で、印刷・発送コストがかかるうえ、封を開けてもらえるかの壁もあります。
開封率を上げるには、差出人名や封筒の工夫が不可欠です。
既存顧客のフォローや、購入履歴に基づいた提案型DMなど、戦略的な使い方でリピート顧客獲得につなげたい手法です。
ダイレクトメールについて、詳しくは以下の記事でも紹介しています。
⑤同封・同梱広告
同封・同梱広告は、通販商品の配送物に広告を入れて届ける手法です。
すでに購入経験のある顧客に届けるため、ターゲットの温度感が高く、レスポンス率も比較的良好です。
自社商品の案内はもちろん、他社との提携で異なるジャンルの広告を挟めば、新たな層の掘り起こしにもつながります。
加えて、商品の到着というポジティブな体験に紐づけて広告が届くため、好印象を持たれやすいのもメリットです。
一方で、物理的に入れられる広告サイズや内容に制限がある点、在庫管理や封入作業などの手間がかかる点は注意が必要でしょう。
同梱広告・同封広告について、詳しくは以下の記事で解説しています。
⑥店頭配布チラシ・ポスティング
地域密着の店舗やエリアでのプロモーションを行いたい場合、チラシ配布やポスティングは今も有効です。
特に主婦層や高齢層を中心とした、インターネット広告に触れにくい層へのアプローチに適しています。
紙でじっくり読まれるため、価格訴求やキャンペーン情報との相性も抜群です。
ただし、無差別な配布では反響が薄くなるため、ターゲットの生活圏やライフスタイルを想定したエリア選定が不可欠です。
配布エリアの選定や折込先の精査を丁寧に行えば、コスト以上の成果が期待できます。
特定地域でのテスト販売や、シーズナルな施策との組み合わせで力を発揮する手法です。
チラシポスティングについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
⑦フリーペーパー・地域情報誌への掲載
フリーペーパーや地域密着型の情報誌は、生活圏に根ざした読者に広告を届けられるのが魅力です。
特に飲食・美容・医療・通販など、生活に密着した商品・サービスと相性が良く、地域性を活かした訴求ができます。
無料で配布されるため読者の手に取られやすく、保存率も比較的高い傾向です。
費用面でも、テレビや新聞に比べると出稿しやすく、初めての紙媒体出稿にも向いています。
一方で、読者層のセグメントがやや広く、広告効果を数値で測りにくい面もあります。
反応率を高めるには、クーポンやキャンペーン情報を盛り込み、明確な行動喚起を加えると効果的です。
フリーペーパー広告について、効果的な出稿のポイントは以下の記事を参考にしてください。
⑧交通広告(電車・バス・駅構内)
交通広告は、通勤・通学など日常の移動中に視認されやすく、繰り返し目に触れることで記憶に残りやすいのが特長です。
特に都市部では接触頻度が高く、地域ターゲティングにも活用しやすい媒体です。
電車の中吊り広告や駅構内のデジタルサイネージなど掲出形態も多彩で、訴求内容に合わせて使い分けられます。
ただし、短時間で伝えきれるキャッチコピーやビジュアルが求められ、表現力が問われる媒体でもあります。
コストは高めですが、認知拡大やブランド訴求を目的とした中〜大規模なキャンペーンに適しています。
新商品の発売やブランドイメージの刷新時など、一気に印象付けたい場面で検討したい広告です。
交通広告について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
通販・EC事業におすすめのオンライン広告5選
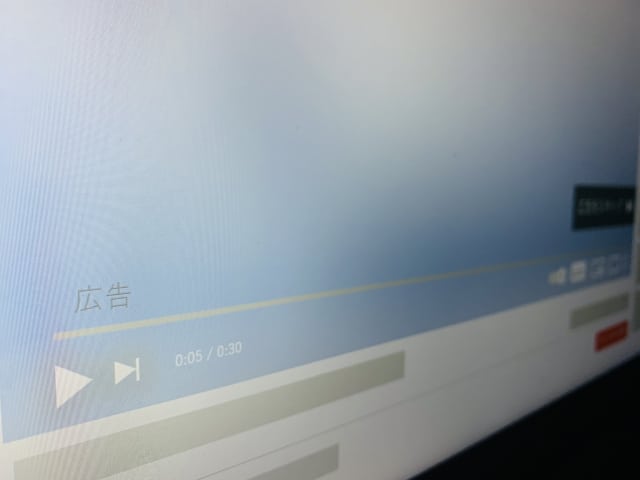
オンライン広告は、配信の柔軟性とターゲティングの精度の高さが魅力です。
ユーザーの属性や行動データをもとに最適な広告配信ができるため、費用対効果を高めやすい特徴があります。
本章では、通販・EC事業において活用しやすい5つのオンライン広告手法を紹介します。
- ①リスティング広告
- ②ディスプレイ広告
- ③アフィリエイト広告
- ④動画広告
- ⑤SNS広告
それぞれの活用ポイントを押さえていきましょう。
①リスティング広告
リスティング広告は、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンに連動して表示されるテキスト広告です。
ユーザーが入力した検索キーワードに応じて表示されるため、ニーズが顕在化している層に直接アプローチできるのが強みです。
例えば、「プロテイン 通販」と検索したユーザーに対し、該当する自社商品の広告を出せば、高い確率で購入につながるでしょう。
また、クリックごとに課金される仕組みのため、無駄な広告費を抑えつつ運用できるのもポイントです。
ただし競合が多い業界では入札単価が高くなりやすいため、効果を見ながらキーワード設計を練る必要があります。
②ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠にバナーや動画などを表示する広告手法です。
検索行動に限らず、ユーザーの興味関心や閲覧履歴、属性などに基づいて配信できるため、潜在層へのアプローチに向いています。
ブランド認知の向上や、商品を知らない層にまず見てもらう入り口として活用されるケースが多いです。
反面、クリック率やコンバージョン率はリスティング広告に比べて低い傾向があるため、目的を明確にしたうえでの設計が重要です。
③アフィリエイト広告
アフィリエイト広告は、第三者(アフィリエイター)が自社の商品やサービスを紹介し、成果が発生した際に報酬を支払う「成果報酬型」の広告手法です。
ブログや比較サイトなどを通じて自社の商品が紹介されるため、広告主の手を借りずに広範囲に情報を拡散できます。
費用は成果に応じて発生するため、無駄打ちが少なく、予算管理がしやすいのがメリットです。
ただし、アフィリエイターの質やモラルによってはブランドイメージを損なう表現がされるリスクもあるため、審査や運用ルールの整備は欠かせません。
④動画広告
YouTubeをはじめとする動画プラットフォームで配信される広告は、視覚と聴覚の両方に訴求できるため、印象に残りやすい特徴があります。
短時間で商品の魅力を直感的に伝えたい場合や、ブランドの世界観を映像で表現したいときに効果を発揮します。
スキップ可能な広告やインストリーム広告など配信形式も多様で、目的に応じて使い分けが可能です。
ただし、クリエイティブの質が成果を大きく左右するため、制作コストやディレクションにも一定のリソースが必要です。
動画広告について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
⑤SNS広告
SNS広告は、Instagram・Facebook・X(旧Twitter)・TikTokなどのSNSプラットフォーム上で表示される広告です。
ユーザーの年齢、性別、興味関心、行動履歴などに基づいて細かくターゲティングできるのが特徴で、商品やサービスに合ったユーザー層へピンポイントで届けられます。
また、広告を通じた直接コメントやシェアの発生により、ユーザーとの距離が近くなるのもメリットのひとつです。
エンゲージメント重視の施策や、ブランドのファンを育てたい場合に特に有効です。
通販・EC事業の広告効果を高めるポイント

広告手法の選定はスタート地点であり、実際に成果へつなげるには運用フェーズでの工夫も欠かせません。
本章では、通販・EC事業の広告効果を高めるポイントを3つ紹介します。
- 商品に適した広告媒体を活用する
- 広告効果をこまめに測定して反映する
- 広告代理店への依頼を検討する
ぜひ、ポイントを押さえて広告戦略を展開してください。
商品に適した広告媒体を活用する
すべての広告手法が、すべての商品に合うわけではありません。
例えば、高齢者向けの健康食品であれば新聞広告やテレビCMのほうが届きやすく、Z世代向けのコスメならSNS広告のほうが親和性が高いはずです。
また、高額商品なら信頼感を高める新聞広告やテレビ広告のインフォマーシャルなどが向いており、日用品なら手軽に訴求できるリスティング広告やディスプレイ広告が効果的です。
商品をプレゼンテーションするとき、どの媒体を通じて伝えればユーザーの関心が高まりそうか。
そこを見極めるだけでも、成果の出方は大きく変わるでしょう。
広告効果をこまめに測定して反映する
広告施策を打ちっぱなしにせず、数値を見ながら調整する姿勢が成果に直結します。
クリック率やコンバージョン率、CPA(顧客獲得単価)などを定期的にチェックし、想定よりも低調な場合はクリエイティブや訴求内容、配信ターゲットを見直しましょう。
オンライン広告であれば、ほぼリアルタイムで数値を把握できるため、PDCAを高速で回せます。
オフライン広告でも、電話やWebからの問い合わせ数、クーポンの回収数などをもとに効果を把握できます。
広告効果の測定について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
広告代理店への依頼を検討する
自社だけで広告運用のすべてをまかなうのは、工数的にもノウハウ的にも難しいケースがあります。
特に複数の媒体を並行して運用する場合、媒体ごとのルールや傾向、最適化手法を把握しきれないこともあるでしょう。
そうしたとき、実績ある広告代理店に依頼すれば、効率的かつ戦略的に広告展開を進めることが可能です。
媒体選定からクリエイティブの企画・配信・リポートまで任せられるため、社内リソースの節約にもつながります。
もちろん、丸投げするのではなく自社の目的や条件をきちんと伝えた上で、二人三脚で進める姿勢が大切です。
通販・EC事業の広告ではスピーディな戦略の見直しが重要

通販・EC業界では、広告の反応が数字で見える分、判断と対応のスピードが成果を左右します。
市場環境やユーザーの反応は日々変わるため、一度決めた広告施策を固定化してしまうと、思わぬ機会損失につながりかねません。
重要なのは、柔軟に見直す意識と、小さく試して素早く改善する姿勢です。
データに基づいて打ち手を更新し続ければ、広告はより精度を増し、販促活動全体の質も高まっていきます。
広告を“育てる”視点を持てば、より効果的な広告戦略が打ち出せるでしょう。
また弊社では、通販事業の方向けに紙で広告を出すための展開パターンや、出稿までの流れ・準備について紹介しています。
詳しく知りたい方はぜひ「通販広告の出稿マニュアル」バナーをクリックして、資料をダウンロードしてください。


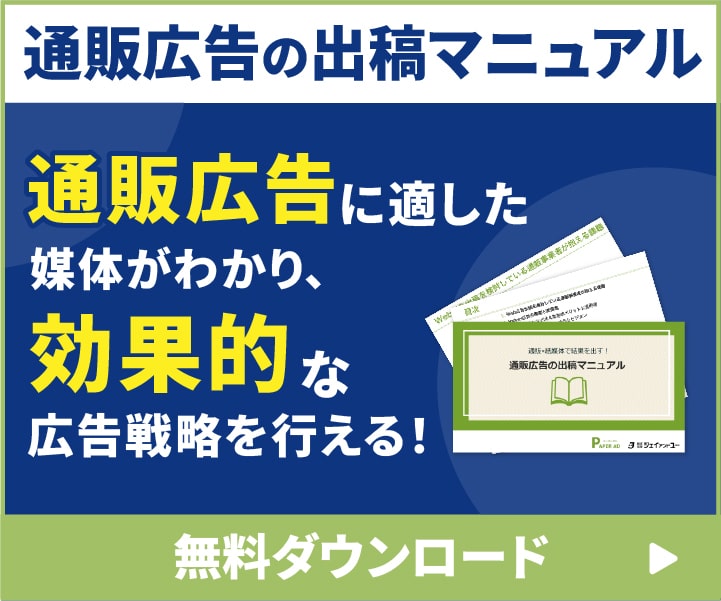










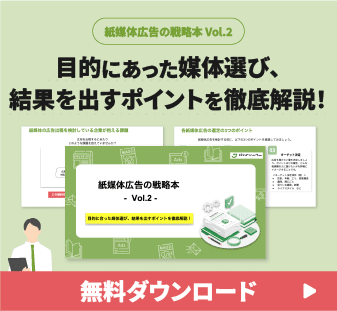

コメントを残す